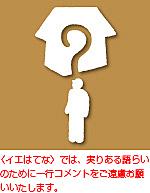 【イエはてな】“リブ・ラブ・サプリ~KIDS” #013
【イエはてな】“リブ・ラブ・サプリ~KIDS” #013
THEME:「扉」「あかり」「イエ遊び」
「今日をちょっと楽しく、特別にすることって何だろう? イエで過ごすいつもの時間を素敵に変える小さな魔法のサプリがあったら……」と展開してきた“リブ・ラブ・サプリ”コーナーの続編のひとつ、キッズ・バージョン。子どもたちと一緒に遊び、学び、楽しむ暮らしのサプリを、テーマに沿って語らいませんか? 豊かな暮らしを創っていく〈イエはてな〉のマインドで投稿ください!
*回答条件* 下記のページをご覧になってご投稿くださいね!
「Welcome to イエはてな」
http://d.hatena.ne.jp/ie-ha-te-na/20080731
テーマ詳細とアイデア例
http://d.hatena.ne.jp/ie-ha-te-na/20110622
※回答欄には、1行目に「 」をつけて、メッセージのタイトルをご記入ください。
※ピックアップ受賞メッセージは、〈みんなの住まい〉サイトにて記事紹介させていただきます。
※回答欄のはてなスターを「おすすめメッセージ」として活用しています。投稿期間中は回答欄のスターのご利用を控えていただけますようお願いいたします。
 48pt
48pt
「夜光塗料のおもちゃ」
夜光塗料の含まれた 人形のおもちゃがあります。
夜 蛍光灯の明かりを消した後、そのおもちゃで
子供を 遊ばせます。
夜、電気を消すと 子供が 怒るので そういうので
早く寝かしつけるのに 役立てました。
ま、興奮して しばらくは その おもちゃで 遊んでますけどね。
 48pt
48pt
「雨の日のイエ・ピクニック」
シトシト雨の降る夕方ってなんだか暗くて、寂しい感じがしますよね。
トタンの屋根を打つ、雨の音だけがやけに大きく聞こえます。
そんな雨の日の夕方のアイデアです。
小学低学年の私に、母が唐突に「今日は手抜き!イエ・ピクニックをしよう」と言いました。
ピクニック?え~イエで~?雨だし、気分が乗らないよ~。
と言いたくなる言葉を抑えて、黙って母についていきました。
ピクニック用のシートを子供部屋に敷いて、夕方の薄明かりとランタンで、いちおうピクニック一式のセットは完了。コップじゃ気分が出ないので水筒を用意。
ピクニックらしくなっていくうちに、だんだんと楽しい気分になってきますよ?
だって、ふだんと違う「夕ご飯」なのですから。
炊きたてのアツアツのご飯を持って来て、母がその場でおにぎりを握ります。
「さァて、中身はなんでしょう。」
「ツナだ!」「ウメボシだ!」「おかかだ!」と兄弟でかじりつきながら当てっこします。
「じゃあ、これを当てたら、スゴイよ!」
なんだろう?兄弟そろって、われ先に当てようとモグモグ食べます。
ところが、食べても食べても何も出てこない(笑)。
おかしいと思って、母を見ると「アハハ!」と笑っています。
ただの塩にぎりだったのですね。
「もうっ!笑」
でも、その塩にぎりの美味しかったこと。
ご飯の甘みと、あたたかさと、ホロリとしたしょっぱさと、海苔の香ばしさ。
「おいしいよ~。」と言ったら、「ツウだね。」と乗せられて、母はかなりうわてです。
シトシト雨の降る暗い感じの夕方だけど、家族みんなが揃って、温かいおにぎりを食べたこと。外が暗いせいか、その明るさがより際立ってみえたのかもしれません。
それにしても、母の手でにぎられた、おにぎりはどうしてこんなに美味しいのでしょう。
雨の日の、あたたかく幸せな思い出として、心に残っています。
 48pt
48pt
「折り紙でつくる魔法のイエ」
赤、黄、青などの折り紙の端をテープでペタッととめると、そこには吹き抜けのイエが。
そして、ハサミで切り込みを入れるだけで、そこには不思議なドアが現れます。
切り込みを入れたドアを開けて中をのぞき込むと、そこは2才の子供にとって無限の空間が広がり続けているようです。
まだ覗いたこともないいろいろな色のイエ(折り紙)で出来た扉を開くと、時には反対側にいるママの瞳のあかりが子供の心に飛び込んでくるのかもしれません。
現代社会が生み出した電気という便利な道具を使わなくても、子供は折り紙のイエの中で魔法のあかりを見つける名人のようです。
折り紙で遊ぶ、魔法のイエサプリ。
子供と遊びながら、ちょっとした日常を楽しくしてくれる折り紙のイエ。
日々成長していく子供の姿を見ているとママも学ぶところが多く、簡単な折り紙で出来たイエなのに、坦々とした子供やママの日常にアクセントを与えてくれるのはそこに魔法がかけられているからなのかもしれませんね。
 48pt
48pt
「心の扉を開く時間」
みなさんは今、お子さんとゆっくりと一緒に会話したりコミュニケーションをとる時間、しっかりと作られていますか?
そんな自分自身も子供のころ、毎日一緒にイエの中で生活してご飯を食べているにも関わらず、親子での本当の心同士の対話をする時間はありませんでした。
決して会話をしない家族だったわけではありません。
ご飯を食べながら会話もするし、朝はおはようと言い合うし、夜はおやすみを告げ合うし、一緒にお出かけも旅行もするし、お買いものだってよくしました。
それは普通の家庭であり、仲むつまじく、ごくありふれた家族の光景です。
しかし、会話をする中で、単なるコミュニケーションは取れていても、それがお互いの心同士の会話・対話ができていたか?という点においては「イエス」とは言えなかった気がします。
次第に自分自身、悩みを抱えたりする時期に達しても、それをどこにぶつけてよいか、寂しさもあったように思います。
皆様はどうでしょう?
自分が子供だったころ、そして現在自分の子供に対してでも。
普通のコミュニケーションは取れていて、それで十分に満足してしまっていて、もっと大事な心の対話ができていないことって凄く多いのではないでしょうか。
最近の家族・親子関係・家庭環境においてはそのあたり少し疑問と不安を感じます。
そこで、私としては子供の心の扉を開くべく、日々の中で親子の心の対話の時間を作ることの大切さを感じます。
http://www.din.or.jp/~honda/e-ikuji19.htm
子育てをする上で、親子の対話が重要だと思います。
ここで言う「対話」とは、心と心が向き合った会話のことです。
親子が心を通じ合うだけでなく、対話によって育てられる能力がいろいろあります。それらが将来子供が生きていく上で役に立つと思うのです。
子育てを含めた生活は忙しいと思います。なかなか子供と向き合った対話をする時間も心の余裕もないかもしれません。
また、いつでもちゃんと対話をしようとしたら大変かもしれません。
1日の中の30分でも、そういう時間をもてたら、と思います。
忙しい時には、「忙しい」ことを子供に正直に伝えることもいい見本だと思います。
子供は親から学び、そして親も子から学びます。
一人ひとり個性があり、マニュアルもなく、大人自身、子供だから大人には何でもわかると過剰な自身を抱くことなく、子供からしっかり学ぶ時間も大事だと思います。
そうして親子の対話の時間をとることによって、子供の心の扉が開かれ、子供自身、自分の感情や本音を誰かに伝えて、そしてその気持ちを受け入れてくれる人がいることを学ぶと思います。
私自身はその過程が無かったためか、大人になっても自分の気持ちや感情を誰かに伝えたりすることが苦手だったりします(^_^;)
子供のころの親子の対話でどれだけ心の扉を開くことができるかによって、大人になってからの生き方もだいぶ変わってくるのではないでしょうか。
是非みなさんも少しだけでも良いので日々に親子の心の対話を増やし、子供の心の扉を開けるよう考えてみてくれたらうれしいです。
余談になりますが、少しだけユニークな扉をv
>子供心がくすぐられる隠し扉いろいろ
 48pt
48pt
祖母とのイエ遊び
私は、両親共働きで祖父母がよく世話をしてくれていました。
田舎だったので、火の玉を見た話しや、狐の嫁入りの話しなどを雨でイエから出られない時にせがんだり、竹とんぼや竹馬なども作り方を教えてもらったりしていました。
こういう世代間を越えて遊びがなりたつということは、とても大切なのではないかと思います。
現在では、おじいちゃんおばあちゃんのほうがWiiの操作を覚えなくてはいけないような時代になってしまいましたが、きっと、もっと素朴になれるポイントはあるんでしょうね。
この夏は、省エネにもなりますし、ゲームの電源をきって、遊びを探してみるのもいいかもしれません!
 48pt
48pt
「懐中電灯」
子供の頃、怖がりで夜寝る時には部屋の照明についてる豆電球をつけっぱなしにして寝ていました。妹と同じ部屋だったのですが、彼女もあかりがついていると安心していたようです。
襖で仕切ってある隣の両親の部屋は当然のことながら電気はつけていないので、夜中、なにかあって両親のところへ行ったとき、襖を開けると光が差し込み、親が目をさますのですが、部屋の奥は黒い空間がぼんやりと見えてきて、なんとなく恐ろしくも感じました。
この豆電球をつけて寝る習慣は結構長く続いて、小学校高学年になってもまだやっていた覚えがあります。
この習慣をやめたのは、妹と別れて一人部屋になった頃だったでしょうか。もう中学生になっていたのですが、流石にこんな年まで豆電球をつけて寝るのは子供っぽいと思い始めていました。でも、消すとなんだか違和感があってちょっと怖いのです。
そこで、どうしたかというと懐中電灯を親にいって買ってもらいました。名目は停電になったときに使いたいということでしたが、本当の目的は布団の中に持ち込むこと。
電気を消して、なんとなく落ち着かなかったら布団にもぐりこんで懐中電灯をつけてみることにしたのです。
そうすると、なんとなく落ち着いてくるのでそうしたら電灯を消して改めて布団から顔を出しました。
そうこうしているうちに、暗闇で寝ることになれて、懐中電灯は使わなくなりましたが、しばらくは何かあったときのお守りのように、ベッドに転がしておいたものでした。
「あかり」というテーマで、そんな子供時代のことを思い出しましたが、自分で調節できるあかりが手元にあれば怖がりのお子さんもちょっと安心するかもしれませんね。
ベッドの側に置く読書灯みたいなものもいいかと思いますが、懐中電灯は子供心に頼りになるものに私には映りました。
もちろん、暗いほうがよく眠れるお子さんもいらっしゃるでしょうから、みんながみんなあかりを欲しがるわけではないと思いますが、昨今は防災の準備も怠ることなくしたいものです。
その一つとしてお子さんにも自分専用の懐中電灯を枕元に置いておくこともいいかなあと思います。
 48pt
48pt
「通気性抜群。ニュージーランド風の2重扉」
子供の頃に通っていた、英語教室はニュージーランドから来た夫妻が建てたイエで、広い芝生の庭から建築物まで、すべて手作りのニュージーランド風。
そのイエで「便利だな~!」と子供ながらに思ったのが、玄関の2重扉です。
まず1枚目は、ふつうの玄関扉です。こちらは子供が入れるよう、常に開いています。
2枚目は、網戸の扉です。日本のサッシに入っているのと同じような網が張られていて、こちらはいつも閉じられています。
網戸を通して、玄関から風入るので、中は通気性がよく気持ちいい~。
ソヨ…ソヨ…と芝生の香りのする優しい風が入ってきます。
それでいて、蚊などの虫が入ってこなくて、本当に便利で快適!!
開けっぱなしの玄関は土埃が気になりますが、そこはちゃんと設計されていて、玄関扉は階段5段ぶんくらい高い位置に設置して、地面の埃が入りにくくなっていました。
1Fの床の高さを利用して、半地下の部屋がありました。そこはビリヤードなどのレクリエーションスペースとして利用されていましたが、日本のふつうの小学生だった私にとっては、大人の雰囲気がムンムンで、ちょっと近寄りがたい感じでした。
そのイエには同い年くらいの、夫妻のお嬢さんが住んでいて、心の中でひそかに「赤毛のアンちゃん」と呼んで憧れていました。
自然を家の中に呼び込む、その暮らしが、プリンスエドワード島の自然の中で生き生きと暮らす「赤毛のアン」と重なって見えたのです。
これが普通のニュージーランドの一般的な家屋なのかどうかは分かりません。
でも、自然を愛するニュージーランド人夫妻の気持ちが伝わってくるような玄関扉でした。
日本では見かけない仕様のドアですが、記憶に残るほどの、すぐれたドアだったので、自分がイエを買う時には、設置してみたいと思っています。
 48pt
48pt
「台風の中の明かり」
先月あった台風2号で我が家は、停電にあいました。
夜から次の日の午前中でした
台風にあうことはめずらしい事ではない島に住んでいますが
こんな長い間停電にあうのはほぼ皆無な事でした。
(結構、大変だったよ・・)
この島は、台風が来る事は何度もあるので・・
もしも、停電にあったときには、懐中電灯と電池で動くラジオを駆使して
停電の中をすごしたいと思いますね。
停電の中でもそれさえあれば暑さは、大変だけど
それなりに家族で落ち着きを持ってすごせるはずで・・。
 48pt
48pt
「光に透ける絵を描こう」
まず、「あぶらひかり」です。これは昔、凧揚げの凧の絵などに使われていた方法の一つで、たとえば武者絵の目の部分などに油を塗ると、そこがお日様の光を透かして光っているように見える、というものです。
これを応用した遊びを、子供のころにやってもらいました。まずお父さんが、白いコピー用紙のような紙に、鉛筆でにゃんこの顔を書いてくれました。目玉が大きくて、お口もニカッと大きく開けている、まんがに出てくるような猫の顔でした。
私に渡されたのは、黄色とピンクの油性マーカーでした。
「お目々とお口だけを塗ってごらん」
「はーい」
私が塗り終わると、お父さんは黒のポスターカラーマーカーで残りの部分を書き加えていきました。黄色の中に縦長の瞳を入れ、顔の輪郭を書いて、塗りつぶしていきました。黒猫さんです。
ちょきちょきちょき。ハサミで輪郭を切り抜いて猫の顔だけにして、それを両面テープで窓ガラスに貼り付けると…。うわぁ~、目と口の色が鮮やかに光を透かす真っ黒にゃんこのできあがり!漆黒の中に黄色とピンクが浮かび上がって、まるでステンドグラスみたい!!私は飼っていた猫を連れてきて抱っこしながら、すごいね、きれいだねと、ずっとそれを眺めていました。
淡色の油性マーカーは、まるで油を塗った紙のように光を透かします。それに対して黒のポスターカラーマーカーは不透明で光を通しません。その対比が、すてきな光のサプライズを作り出してくれたんですね。
少し大きくなって、その経験を夏休み工作に応用しました。豆電球を使った電気スタンドのミニチュアです。まず真っ黒い画用紙のような紙をランプシェードの形の展開形に切り取りました。そこにカッターで三日月やお星様の形を切り抜き。裏から色んな色のセロファンを貼り、くるんと丸めるとランプシェードのできあがりでした。「あぶらひかり」とはちょっと違う作り方でしたが、色を透かして漏れてくる光の美しさをもう一度味わってみたくて、こんな工作をしてみたんです。
もう一つ、日本の行灯みたいな物も作りました。本の写真を見ながら割り箸で骨組みを作り、そこに和紙…というか習字用のお半紙を貼って、透明水彩絵の具で朝顔の絵を描きました。これの中にも豆電球を入れました。
夜、暗くなるのを待ってわくわくしながら点灯してみたら、どちらもすごくきれい!!色セロファンを通した光も、透明水彩を通した光も、暗闇の中で本当に美しく光りました。これらは今でも心に残っている工作です。
皆さんも、光に透ける絵を描いて、窓に貼ったり、豆電球…今の時代だと発光ダイオードなのかな、そういうのを入れた工作を楽しんだりしてみませんか。どんな紙に、どんな用具で色を付けるときれいに光が透けて見えるか、色々試してみてくださいね。和紙に本当に油を塗って光らせてもきれいです。
 48pt
48pt
「牛乳パックで電車ごっこ」
牛乳パックの各辺の比率は、ちょっと電車の車両に似ていると思いませんか?そこで私はこれで電車ごっこを楽しんでいました。
材料は、車両1両あたり牛乳パック2つ。上部を切り取り、中をよく洗って乾かします。乾いたら片方に新聞紙をよく揉んでギュッギュッと詰め込みます。これは潰れ防止用。続いてもう一方のパックを蓋のようにかぶせ、きついですがグイグイ押し込んでいくと、これでなかなか頑丈な車体の出来上がり。
連結器は毛糸で作りました。一方は先端を数回折り返して大きな結び玉を作った物。もう一方はそれが差し込めるループ状。それを車体の下にガムテで貼り付けて連結器としました。あとは車体をくるむように紙を貼り付け、窓や扉を書き、好きな車両の色を塗って完成です。側面下方には車輪や、何かの機械に見えるような物も書きました。
こうして作った車両をいくつか連結して、床の上で楽しく電車ごっこ。5両くらい連結すると長くてかっこいいですが、引っ張って遊ぶのが大変なので、3両編成くらいがちょうどいい長さでした。私は6両作って、3両×2編成として遊んでいました。毛糸の連結器で自由に編成が変えられるところが楽しかったですね。
これを作ったのはたしか2年生くらいの時だったと思いますが、作るのも楽しく、遊ぶのも楽しく、かなり熱中したのを覚えています。親に電車の路線図を書いてもらい、それを見ながら床の上に見えない線路を思い浮かべて楽しみました。
「次は新宿~、新宿~、この電車は新宿から中央線に入ります~」
緑の車両が実際には有り得ない直通運転。時々、父と母も一緒に加わって、この電車で箱根まで行こうとか、色々な楽しい架空の旅にも付き合ってくれました。
牛乳パックで作った電車でごっこ遊びなんて、ちょっと幼稚園児みたいですが、作る、遊ぶ、そして空想を楽しんだり地理を覚えたりといった楽しみが加わると、小学生になっても十分楽しめる要素が満載です。鉄道のロマンは大人もはまってしまう世界ですから、もしかするとこの電車の架空の旅には、お父さんお母さんの方が熱中してしまうかもしれませんね。
 48pt
48pt
「ロウから手作りのキャンドルで地球の恵みのあかりを体験」
ロウは手作りできるって知ってました? 木の実から、本当にあかりが灯せるロウが取り出せるんです。
日本の伝統的な蝋燭につかう蝋の原料はハゼノキの実。昔は近い種類の植物であるウルシの実も多く使われました。どちらも蒸して絞ると、蝋がとれるんです。椿の実などから油を絞るのとやり方が似ていますね。
実をたくさん集めることが出来れば、この作業は家庭でも行えます。でも困った事が一つ。ハゼノキもウルシも、かぶれるんです。このかぶれはウルシオールと呼ばれる揮発性物質によるアレルギー反応で、体質によっては木の近くに行っただけでかぶれてしまうことがあります。ですから、これはちょっとお勧めできませんね。
そこで、ヤマモモの登場です。なんとヤマモモの実からも、立派な蝋がとれるんです。ヤマモモは主に関東以南の中山間地などに自生しています。またヤマモモは、海を守るための植林にも多く用いられてきました。海岸近くの山にこれをたくさん植えて、土砂の流出を防いだんですね。ヤマモモは発芽率が良く、痩せ地でも良く育ち、実も食用として楽しめますから、こういう目的にも最適だったんです。結実の時期はちょうど今頃です。
もしこの実がたくさん手に入ったら・・・・。もちろん食べたいですよね。ヤマモモの実はとても美味しいです。でも、もし食べきれないほど実が採れたら!! その時は蝋をとってみましょう。ヤマモモの実をグツグツと鍋で煮ると、油のような物が浮いてきます。それを冷ますと、ほーら、固まりました。これがヤマモモの蝋なんです。
実の量が少ないと、それこそ雀の涙くらいの蝋しかとれないかもしれませんが、ここではとりあえずある程度の量が確保できた物として、これでフローティングキャンドルを作ってみることにしましょう。
まず、蝋を水から引き上げて、よく乾かしておきます。その間に、
を用意しておきましょう。
蝋を溶かすための小さな金属カップには、アルミ製の空き缶などが使えます。キャットフードの小さな缶などが大きさ的にピッタリです。缶の上のリング部分をハサミで切り取ってしまい、縁の一個所をラジオペンチなどで抓んでクイッと引き出して注ぎ口を付けてやると使いやすくなります。缶の切り口で手を切らないよう、注意して作業して下さい。軍手をはめて作業すれば安全性が高まりますね。小さなお子さんの場合は、大人の人がやってあげてください。
芯にする糸は、できればキャンドル芯専用として作られた物を用意するのがお勧めです。キャンドルの芯として作られた糸は、よく見ると、ランプの芯と同じような編み上げ構造になっています。これが溶けた蝋を安定して吸い上げて燃焼させてくれるヒミツなんですね。撚っただけの糸とは、ちょっと作り方が違うんです。どうしても手に入らなければ、凧糸などで代用出来ない事もありませんが、不安定な燃焼による炎の揺らぎや黒煙の発生などは起こりやすくなります。素材は必ず木綿としてください。絹や毛糸などの動物性繊維や合成繊維などは使えません。
チョコ型は、一口大のチョコを作る時に使う物。食べ物からとった蝋ですから、お菓子作りの道具が安心して流用できますね。さらにヤマモモからとる蝋は融点が40数℃と低いので、プラスチック製の型でも大丈夫なんです。
割り箸は蝋が固まるまで芯を挟んでおくために使うだけですから、他の物を流用しても構いません。
さて、作りましょう。まず蝋を小さな金属カップに入れて湯煎します。この時、お湯を蝋の中に入れてしまわないように注意。蝋が溶けたら、適当な長さに切った芯を浸します。よーく蝋を染み込ませてください。芯を引き上げて、ピンと真っ直ぐにして冷やします。端を1cm弱、直角に折って、L字型にしておいてください。
あとは、こうして作った芯をチョコ型の中心に立てて蝋を注きます。この時、割り箸を型の上に渡して、芯を挟んでおくんですよね。あ、もちろん芯は、L字型に折った側が下ですよ。冷えてしっかり固まったら、型から抜いて、これでフローティングキャンドルの完成です。
このキャンドルは水盆に浮かべて火を灯します。倒して火事になったりする危険性が少ないタイプのキャンドルです。原料は100%自然の恵み。しかも蝋から手作りの完全なハンドメイド。こんなキャンドルで夏の一夜を過ごしたら素晴らしいと思いませんか!!
実際には、たわわに実るヤマモモの大木を見つけられる人は少数でしょう。実が手に入っても、ほとんどは食べてしまうと思います。残った実も、普通はジャムか果実酒ですよね。でもいつか、それでも使い切れないくらいのヤマモモが手に入ったら、その時は甘酸っぱい美味しい実を楽しみながら、手作りキャンドルで過ごす素晴らしい夜!!
とりあえず今は、ヤマモモから蝋がとれるんだということだけ、知っておいてください。いつか実現する時がくるかもしれません。ヤマモモのキャンドルは、石油が原料のパラフィンで作られた物と違って、燃焼時の匂いも爽やかです。お子さんと一緒に、いつか作ろうねと、夢を膨らませてみてください。
 48pt
48pt
「みんなで遊べるジェスチャークイズ」
日本のテレビ史上初めてのクイズ番組は、「家族ゲーム ゼスチュアー」という番組でした。内容は、身振り手振りだけで出題文を表現し、それを回答者に当てさせるというもの。この番組はNHKがテレビの本放送開始した1953年に4回放送され、大好評を博したそうです。その後週一回のレギュラー放送に昇格。タイトルを「ジェスチャー」に改めて、テレビ初期を代表する人気番組となりました。
その後も類似のクイズ番組がいくつか民放で放送されていたようでしたので、ジェスチャークイズといえば、おそらく実際の番組は知らなくても、たいていの人が「あぁ、あれか」とご理解いただけることでしょう。
とにかくこれは人気番組だったので、イエ遊びとしてこれを真似することも大流行だったそうです。私も育った時代は違いますが、同じような事をして遊んだ記憶があります。
出題文は、最初は分かりやすく表現ものから。たとえば「走っている犬」とか「木に登っている猫」みたいな感じ。だんだん慣れてきたら、少し長めの文章にしていきます。季節感のあるお題がいいですね。夏なら「海の家でラーメンを注文して、汗を掻きながら食べているお父さん」とか、秋なら「お月見のお団子を食べながら月を見ないでテレビを見ている子供」みたいな感じ。
さぁ、皆さんならこれを身振り手振りだけで、どう表現しますか?回答は出題文とピタリ一致しないと正解になりませんから、出題文は必ずメモに書いておき、ジェスチャーを演じる人はそれを見ながら正確に伝えていきましょう。
ただし、素早く上手に意思を伝えて行くには、倒置法的なテクニックも使います。文章を頭から伝えていこうとせず、先に全体のイメージが掴めるものから表現していくのです。たとえば「木に登っている猫」なら、先に「猫」を当てさせてから、箱を持ち上げて隣りに置くような仕草「それはおいといて」をやり、あらためて「木に登っている」を表現する、といったやり方です。「に」などの助詞は指を二本立てて「2」といった、同音異義の語に置き換えても構いません。テレビでは、喉を指さして「の」を表現するといったやり方がたくさん使われていたようです。
ジェスチャーの面白さは、同じ語を表現するのにも、一人一人全然違ったやり方があるというところです。思いもよらない面白い表現がどんどん飛び出してくる。ここが楽しいんですね。それに、大きな動作や表情で、伝えたい言葉や、当たり外れ、近いけどちょっと違うといったニュアンスを表現していく必要がありますから、のってくるとどんどん大胆になっていくのも面白さの一つです。
そして何度となくこの遊びを繰り返しているうちに、表現がどんどん豊かになって、そのうち自分独自の表現の法則が生まれていきます。自分独自の非言語コミュニケーションの確立です。それを一緒に楽しんでいる人達と共有していく喜び。ここに絆が生まれていきます。
大げさではありません。本当に、この遊びを繰り返していると、そこに「コミュニケーション文化」が生まれていくんです。同じ文化の共有。本当に絆が深まりますよ。
なんて難しいことを考えなくても、紙と鉛筆、あとは体さえあればすぐ出来るジェスチャークイズ。大人も童心に還って、抱腹絶倒の時間が過ごせること請け合いです。
 48pt
48pt
「イエの中でイエ遊び」
小さい頃から見立て遊びが好きで、特に「お家ごっこ」が昔から大好きな息子。
積み木やブロックで、イエを作り、その中でブロックで作ったロボットや乗り物、動物で遊んでいた。
最近はさらにその工夫に磨きがかかったきた息子。娘もそれを見ながら真似っこして遊んでいる。
そんな子供たちが熱中して遊んでいるのを見るのが自分は嬉しく遊んでいる背中をながめているのが至福の時だ。
本当は前からじっくり眺めたいが、自分(親)の視線は時として遊びを邪魔することとなる。
今年、息子が年中に上がり、たびたび一緒に遊ぶようになった年長さんの部屋では、大きなドールハウスがあり喜んで遊んでいるそうだ。
しかし、木のお洒落なドールハウスは、小さいながらもなかなかの高級品w
色々調べてみて、ハンドメイドのドールハウスなどの作り方が載っている本を発見!
これを見ながら近いうちに息子たちと一緒にドールハウスを作るのを夢見ている。
・・・・
まずは土台作りから。
本格的なものは板を適当なサイズに切って作るのだが、手軽に作るのならプラダンボールや二重ダンボールなどを利用してもいいだろう。
でもせっかくなら最初に挑戦したいのは木を使ったシンプルな箱型のワンルームw
三面の壁の上に乗せた屋根は取り外せるようにしたい。
そして同じタイプのイエをいくつか作って、重ねられるようにしておけば、ある時は二階、三階建てのイエになり、
家族や友達と一緒に遊ぶ時には分けて数軒のイエにして遊ぶのも良し。片付けるのにも便利だ。
用意するのはハウスの材料となる木材と、手の一部となる道具たち、小刀・のこぎり・かなづち・釘、錐にカンナ・金尺など。
今までにも使ったことがある道具もあるが、初めて触る道具も沢山ある。でもきっと使っていくうちに、徐々に上達していくだろう。
ケガをしないように扱い方の注意はしつつ、基本的には作業は自由にさせてやりたい。
親父が自分に教えてくれたように工具の使い方を、今度は自分が息子に教えたい。
近頃は、小学校の授業で工具に始めて触り、上手く使えずケガをする子も多いそうだ。
イエでは音や場所の問題もあり、また必要にもせまられないので金槌や木槌を使ったりする機会が少ないからだと思うが、
工具の使い方は体感して覚えることが一番だと思うので、ドールハウス作りはまたとない工具を使った物作りの腕を磨くチャンス。
おまけにドールハウス作りは木工あり、ラグや人形の服、布団などの裁縫あり、食器や食材などの粘土細工に、壁紙やベッドなどの
紙細工ありと物作りの集大成でもある。
ドールハウス作りを極めれば、応用がきいて色んなパターンの物を作り出せるようになる。
また、家具や小物などアイテムを増やすたびに、確実に遊びの幅が広がっていき、とても楽しいものだ。
ただ、工夫することも大切で、欲しいと思ったものをすぐ作るだけではなく、あるもので代用応用することも大事なのである。
階段や机はブロックやレンガ積み木で作ったり、マッチ箱に紙を貼って机やベッド、テーブルに見立てたり。
昔、自分と弟が小学生の頃、共同で作ったドールハウスは三階建てで、先にあげたように分割できる仕様で、
床板以外はダンボール製だったが、こだわりの天井につけた照明代わりのライトはちゃんと光った。
もちろん作るうえで、自分達だけでは難しい部分があり、その時々で親父にも協力をあおいだのは言うまでもない。
こうして親子で協力して作った作品は丁寧に扱い、また壊れても直し、新たなアイディアが浮かぶとリフォームもしたw
ドールハウスは作るだけではなく、自分以外のものや人になりきって遊ぶことで、心の成長にもつながっている気がする。
そんな子供たちと自分はこれからも一緒に遊びつつ、そして時にはそっと支え、見守っていきたい。
 48pt
48pt
「魔法のあかり」
あかりといえばキャンドルと、その繋がりで提灯が浮かびました。
提灯は街灯がない時代、夜道を歩く時に竹と紙という炎に弱い素材で、風に弱い炎を守り、明かりを携帯するための物。
使用しない時は折りたたみ、薄くしてしまっておき、使う時には上下に引っ張ると大きくなります。
この提灯、発明された当初は今の携帯電話に匹敵するような画期的な商品ではなかったかと思います。
現代、提灯は灯りとしてだけではなく、主に広告に利用されながら残っています。
そして日本で一番有名な提灯といえば浅草寺の雷門の提灯ではないでしょうか。
調べてみると雷門の正しい名前は「風雷神門」、三社祭で提灯の下を神輿が通る際には提灯を持ち上げて少し畳んでいるそうです。
ちょっと勉強になりましたw
しかし私にとって提灯といえば、雷門や、焼き鳥屋の赤提灯…ではなくお祭の提灯なのですw
先日行われた熱田神宮のお祭りでは、子ども達と一緒に門に据えられた無病息災を願う365個もの提灯を見て、感動しました。
参道の屋台の看板提灯を見ても、子ども達は大はしゃぎしていましたが^^;
提灯の灯りがついた状態を子どもが見ることが少ないもの、空やお店の前に明るく飾り付けてあるだけで、
何だかいつもと違う雰囲気にワクワクドキドキしていたのでしょう。
その様子を見て私までついつい昔に戻り、子ども達と一緒にはしゃいで、お祭を楽しむことができました。
そして後日入った喫茶店で娘が「お祭り!」と言ったので、
どこにお祭が?と思って、よく見てみると、そのお店の壁には全国の「土産提灯」がいっぱい飾ってありました。
旅好きのマスターが、出かける度に購入された地名入りの提灯が飾ってある、面白いコーナーになっていまして、下の子は、その提灯をみて、先日のお祭を思い出したようでした^^
私が小学生の頃、学区の子ども会と近所の商店街が協力して、年に一度八月半ばに商店街で開催された夏まつりがありました。
一番印象に残っているのが弟と二人で行った年です。
毎年母と弟と一緒に行っていたお祭りですが、ある年、母は祭りの実行委員のため一緒には行けなくなりました。
父の帰りも遅いため、私達は家で留守番になりそうだったのですが、毎年楽しみにしている私達のために、
祭りに来たら母のいる場所に寄ること、弟と手を繋いで一緒に行くこと、お金を落とさないように気をつけることなどと言い含められ
子どもだけで夜の祭りに行くことが許可されました。
そのころの夜は今よりも、もっとずっと暗かったという印象があります。
暗闇に浮かぶ提灯の明かり。
その明かりを遠くに見ただけで、二人の歩みは速まり、気持ちは既に祭りの中にありました。
弟の手をしっかり繋ぎ、首から提げた小銭入れを握りしめ、まず、お店の名前の書いてある提灯を目印に町内の屋台を一巡。
その間に、金魚すくいの金魚の種類や元気のよさ、たこ焼き屋のたこの大きさはどこが一番大きいか。
お好み焼きと焼き蕎麦、どちらを食べるべきかwデザートはかき氷かリンゴ飴か、はたまたわた菓子にするのかなどを
二人で真剣に検討しましたw
地元なので、同級生の子も沢山来ていて、お店の情報交換もしました。
そして、いくつかの屋台に目星をつけ、母からもらった、お小遣いの使い道を決定。
意を決してお目当ての屋台に行きます。
たこ焼きに、五平餅、デザートにカキ氷を食べ、金魚すくいは友達がするのを眺めつつ、怪しい小物を売るオジサンの口上に耳を傾ける。
無事、案内所にいた母とも出合い、少しだけ分けて貰った枝豆もご馳走でした。
この時分の私にとって、提灯のあかりの中で繰り広げられる祭りの世界は、いわば「夢の国」。
大人の目で見てしまえば提灯の明かりは、なんてことのない、ただの照明に過ぎないかもしれません。
でも子ども心には、日常から離れた別世界へと誘ってくれた「魔法のあかり」でした。
提灯のあかりには、子どもの心踊らせる魔力があると思うのです。
大人になって魔法が解けてしまう前に、子ども達には不思議な提灯のあかりを沢山体験をさせてあげたいです。
 48pt
48pt
「心に『開けるための扉』を新しく作ろう」
今回は、具体的な暮らしのノウハウやアイデアの提案ではありません。でも「扉」というテーマで思い出した話がありますので、それをここにご紹介させていただきたいと思います。
小学校5年生の時だったと思います。夜、友だちから電話があり、クラスの一人が家出したことを知りました。
「居場所は知ってる、A子から電話があった。家の人はまだ動いていないようだ。でもあと何時間かすれば大問題になる。どうしよう」。
A子というのは私たち男子とも比較的仲が良かった女子のことです。家を出てしまったのはその友だち。やはり女子でした。その子を仮にB子とします。
「でB子の居場所は?」
「○○駅前。今A子が引き止めてるって」
「他に知ってるやつは?」
「まだ俺とA子とお前だけ」
「ならまだ間に合うな、行くか?○○駅」
「行くしかないだろうな」
○○駅というのは私たちの住んでいる所からは離れた、子供にとってはかなり遠くでした。時間も時間なので、私はこっそりと家を出ようとしました。しかし自転車を動かす音を聞きつけられて、父に「どこに行くんだ」と呼び止められてしまいました。仕方なく、今は何があっても絶対に内緒だぞと前置きして事情を話すと、父は少し考えて、「車を出してやろう」と言ってくれました。
電話をかけてきてくれた友だちとは最寄りの駅で待ち合わせでしたので、そこで友だちを拾って○○駅へ。車中で、私たちは少し話し合いました。
父「何か思い当たることはあるのか?」
私「詳しい事情は何も分からないけど…」
友「あそこ、ほんとの親子じゃないんだよな」
父「家族、うまくいってないのか?」
私「そんなことはないと思う」
友「うん、普通の親子以上に大事にされてると思うよ」
父「そうか、まぁ、ゆっくり話を聞いてやれ。時間は気にしなくていい。君の家にも電話しておくから心配しなくていいよ」
父は、その辺のハンバーガー屋にでも入れと、お金まで渡してくれました。そしてさらに一言。
「一度閉ざしてしまった心の扉は無理にこじ開けようとするな。ゆっくり時間をかけて新しい心の扉を作るんだ。分かるか?」
よく分かりませんでしたが、私たちはウンと頷きました。
○○駅前に到着。父は離れた所で車を止め「お前らに任せるから行ってこい」と言ってくれました。駅の中に入って探してみると、A子とB子はすぐ見つかりました。無言で立っていた二人を誘って近くのハンバーガー屋に。店の前にはもう父が待機していました。私たちはそっと目で合図を交わして店の中へ。父はガードレールに腰掛けて待っていてくれるつもりのようでした。
それから、私たちはポテトをかじりながら、色々と事情を聞きました。きっかけは些細ないさかい。でも、ずっと心の中に鬱積していたものが一気に吹き出して、家を飛び出してしまったということのようでした。しばらく沈黙の時間が続き、そして友だちが言いました。
「よく分かんないんだけどさ、俺さっきいい言葉を聞いたんだ。閉じている心の扉は無理に開けなくていい、代わりに新しい心の扉を作ってそれを開けろって」
また沈黙が続きました。B子が泣き出しました。A子が言いました。「おじさんやおばさんのこと、きらい?」。B子は首を横に振りました。「じゃ、何でも話し合おうよ、開くための新しい扉を心に作ろう」。B子はゆっくりと首を縦に振りました。「家に電話しようよ、きっと心配してるよ」。B子はゆっくりと立ち上がって、店内の電話に向かいました。
ほどなくしてB子のおじさんとおばさんが迎えにやってきて大団円。A子も一緒について店を出て行きました。それを見届けて父が入ってきて、アイスコーヒーを注文。
「うまくいったみたいだな、作れたか、新しい心の扉」
「うん!!」
私たちは声を揃えて答えました。
「心の扉はいくつあってもいいんだ。閉ざす扉もあっていい。でも一つだけ、開けるための扉も作っておこう。な」
「うん!!」
再び声を揃えて答えました。それからは「心に『開けるための扉』を作ろう」が、私たちの合言葉になりました。
 48pt
48pt
「お気に入りの本の扉絵を描こう」
扉絵。英語で言うとfrontispiece。本の扉部分を飾る絵のことです。コミック雑誌などの場合は、各作品の冒頭に付されるタイトルや作者名が入ったページのことを扉絵と呼びますね。それらは作品の内容を読者に印象づける、とても大切な役割を持っています。でも、扉絵が無い本もたくさんあります。子供の読む本も、学年が進むにつれて文字だけになっていき、扉絵のある本が少なくなります。
本をたくさん読みなさい。父も母もそう言いました。でも、マンガと違って、文章だけの本は、その世界に入り込むのに時間がかかります。子供はけっこうそれが苦手。特に挿絵がない本は、なかなか読む気が起きません。
「またマンガばかり読んで、少しは本も読みなさいよ」「だってぇ、絵がないとお話しに入っていけないんだもん」「なら自分で描けばいいじゃない」「あ…面白そう」。
ためしに、もう読んでお話しが頭に入っている本でやってみることにしました。画用紙を本と同じ大きさに切って、そこに色鉛筆で描いてみました。描けたら本に挟み込もうと思って、丁寧に時間を掛けて描きました。「出来た~!」。本の表紙の次の所にそれを挟み込んで母に見せに行くと、立派な扉絵が出来たねと褒めてくれました。
「扉絵?」「そうよ、こういう所に入っている絵をそう呼ぶの。ちょっと待ってて」。
母が持ってきたのはエアメール用の便箋でした。薄い、透けるような紙です。
「本当はトレーシングペーパーっていう紙をかけるんだけどね」。
絵の裏に便箋の端を貼り付け、表側に折り返して絵の表面を覆って、サイズを合わせて綺麗に切ってくれました。
「ほらこれで豪華になったし、色鉛筆の粉で本が汚れることもないわよ」。
やったー!すごいー!私は大喜びで、すぐまた他の本の扉絵にも挑戦しはじめました。
そのうち描く本が無くなってしまったので、それまで持っていながらちゃんと読んでいなかった本も読みはじめました。すると不思議。どんな絵を描こうかなと思いながら読んでいると、文字だけの本なのに次々と物語の情景が頭の中に浮かんできます。私はどんどんお話しの中に引き込まれていきました。
一冊読んでは扉絵を描き、また一冊読んでは扉絵を描きを繰り返しているうちに、すっかり読書が好きになっていきました。読み終わってから描くこの扉絵は、いわば絵による読書感想文。本の余韻を楽しみながら絵を描く時間も、より物語の世界を深く理解させてくれる素敵な時間になりました。
私はけっして絵が上手な子供ではありませんでした。でも楽しんで描ければそれでいいんです。読んだお話が好きであればあるほど、いい絵が描けます。その頃の本も、自分で描いた扉絵も、みんな大切にとっておいてあります。大人になった今、それはとても大切な宝物です。絵が上手でなかった子供でも、そう思える絵が描けるんです。それは、素晴らしいお話しの力を借りて描いたからだと思います。
読んだ物語の絵を描いてみる。それで本の扉を飾ってみる。皆さんのお宅でも、ぜひやってみてください。本の世界も絵の世界も、何倍にも膨らみます。
 48pt
48pt
「心だけならすぐに行ける、地図という名のどこでもドア」
一番欲しい扉は?と聞かれたら、私は今でも「どこでもドア」と答えます。そんな私にとって、地図と百科事典が心の世界の旅の扉を開いてくれる「どこでもドア」でした。特に世界地図が好きでした。
知らない地名が出てくると、まず事典でそれを調べました。最初に調べたのはブレーメン。ブレーメンの音楽隊の話を思い出して、いったいどこの話だろうと興味を持ったのでした。事典で調べてみたらドイツでした。ブレーメン州というのがあって、その首都がブレーメン。事典には写真も載っていました。石畳の広場やクラシカルな建物が本当に童話の世界みたいでした。国が分かったので、続いて開くのは世界地図です。どこかなどこかな。ありました。上の方、北海に近いあたりです。地図と事典の写真を交互に眺めながら、ロバや犬や猫やニワトリと一緒に旅をしている気分に浸りました。
そんなことがきっかけとなって、ほかにも色々な場所のことを調べてみました。テレビなどで知らない地名を聞くと、食事中でも早く調べてみたくてうずうず。食べている間に聞いた地名を忘れないようにと必死だったのを思い出します。
そのうち、ニュースなどにも出てこないような島に興味を持ちはじめました。世界中には知らない島がたくさんあります。特に南洋の方には、小さな島がすごく離れて点在しています。こんな所に人が住んでいるのだろうかと思って調べてみると、ちゃんと人が住んでいたりします。すごいなぁ、最初にここに住み着いた人はどうやってここまでたどり着いたんだろうなどと思いを巡らせているうちに、地図による島巡りが趣味になっていったのです。
特にポリネシアが好きで、その島々のことを色々調べました。ハワイ、ニュージーランド、イースター島というすさまじく離れた三個所を結ぶ範囲内がだいたいポリネシアです。そんな広い海域に共通の文化を持つ人々が散らばっていることが驚きでした。特に興味を持って深く調べたのはトケラウでした。最も高い所で海抜2mくらい。全ての陸地がサンゴ礁の上という不思議な三つの島からなる地域です。詳しいことがなかなか分からないので、図書館にまで行って調べたりしました。そして、どんな島だろう、いつか行ってみたいなぁと夢を膨らませました。
図書館で調べたことをノートに書き写したのがきっかけで、イエでも調べたことをノートにまとめるようになりました。ノートにまとめるというと勉強みたいでつまらなそうですが、趣味ですからこれが面白いのです。調べたことが貯まっていくごとに、旅をした場所が増えていく気持ちになりました。
白地図が手に入ったので、調べたことのある場所に印を付けてみたりもしました。あれ、アメリカが少ないです。よし、今日はアメリカ横断だ!こんなふうに休みを一日潰して、地図上の「どこでもドア」を開き続けたこともありました。
今は百科事典のないイエが多いと思います。代わりに、調べ物はネットですね。でもネットを子供が自由に使えるイエも少ないと思いますから、もし子供が地図の楽しさに目覚めたら、ぜひ大人が調べ物をサポートして、一緒に心の世界での旅を楽しんでください。地図を開く。心の世界での旅の扉を開く。これは本当に楽しいです。
 48pt
48pt
「子どもと沢山の扉」
昔、テレビの「ドラえもん」を見ていて、私も『どこでもドア』があったらいいのにな~ってつぶやいていました。
そうしたら母親が、「あなたにはもう『どこでもドア』、あるじゃない。実はお母さんも、持ってるのよ」。
って言い出したので、私はすごくビックリしました。
そして「あのね、それは本なの。本や絵本は、その扉を開くと、そこに居ながらにして、色んな世界に行けるでしょ?
だから本が『どこでもドア』なんだよ」って説明してくれました。
私は本を開くと物語が飛び出してくるというより、向こう側に入り込む感覚だったので、
同じく本好きの私の母親ならではの説明に、ものすご~く納得。
本の世界へ表紙の扉から中に入り込み、時々裏表紙ならぬ扉を閉じて、こちらの世界へ戻ってきます。
そして物語が終ったら本は本棚へ。
いつかまた、その本の世界へ行きたくなったら、また本棚から出して扉を開くという・・・。
本の中では、私たちが行ったことも見たこともない町で、知らない友だちや色んな仲間と出会えたり、ジャングル探検や宇宙旅行も
できちゃいます。
そして本からはストーリー以外にも大事なものに出会えます。それは沢山の素敵な言葉。
私が悩んだ時とか、何かあった時に「そういえば、あの時の一言が欲しいな」と思ったら、
本棚から、その大好きな本を出せば1年経っても10年経っても、30年経った今でも、そこで同じように同じ言葉を
言ってくれているんです。
もちろん今と10年前では言葉の受け止め方は違うでしょう。同じ日であっても1回目に読んだ時と読み終えてから
2回目に読み返した時とはまた違った印象になることもあります。
今はまだ文字が読めない娘が、読んで~と持ってきた絵本は喜んで読んであげているけれど、
娘が読んで~と持ってきて、喜んでくれるから読む本とは別に、
まだよくわからない話かもしれないけれど、大人、つまり私と夫のの伝えたい思いの入った本を
「今はわからないかもしれないけど、私たちが伝えたい話だから読むわね」ということもあります。
でも本当は娘には早く自分で本を読めるようになってほしいな~って思っています。
いえ、これはけっして読み聞かせるのが面倒だからっていうわけではないんですよ。
私が娘に本を読み聞かせるっていうことは、私の頭の中に浮かべた感覚、感情が自然に出ちゃうので、
自分で読んだときと本のイメージが違うかもしれないって思うんです。
そして 図書館や本屋さんに行くと本が自分を、呼んでいるってことありませんか?
なんだか分からないけれど、この本を買いにきたわけじゃないのに、本の方から呼ぶ声がする。
ふと見ると、「あ~私、これが読みたかったんだ!」っていう運命の出会いみたいなことも結構あるんです。
それが、本の力でもあるし、物語の扉を開ける瞬間の喜びなんですよね。
もちろん、その時には自分の手でその扉を開けて、中の世界に飛び込んでいって欲しいのです。
人生は1度きりですが、本にはそれぞれの生き方がつまっていて、物語が100冊あったら、100通りの人生を体験できるんです。
 48pt
48pt
「手影絵で遊ぼう!!」
「あかり」と「イエ遊び」が合体したら影絵です。“リブ・ラブ・サプリ~KIDS”の第一回目で「色の光で影絵」ということで子供のころに父母が見せてくれた影絵シアターのことを書きましたが、今回はもっとシンプルな手だけで影を作る手影絵です。
こちらは日本に昔からある手影絵のやり方を解説してくれているページの一覧です。ブログと同じように新しいエントリーから掲載されているので、古い方から順に見ていってください。
http://hug.kids-station.com/yomimono/howtoplay/archive001.html
こうした手影絵のいくつかは、皆さんも子供のころにやったことがあるのではないでしょうか。もしかしたら幼稚園や保育園などで、先生がやって見せてくれた思い出がある人もいるかもしれませんね。
手影絵は海外にもあります。外国ではHand Shadowsなどと呼ばれて、マジックと同じようなショーとして上演されることもあるようです。こちらはおそらくそんな海外のHand Shadowsを解説していると思われるページです。こちらも図解で、とてもわかりやすくやり方を解説してくれています。
http://smile-pro.net/articles/2008/08/tekagee.php
私は何年か前にこのページを見つけて、懐かしくなって密かに練習していたんです。それを夏休みに親戚の子供たちに見せたら大好評でした。私は形を作るのが精一杯で、影をスムーズに動かしたり、ストーリー仕立てにして見せることなどはとても無理でしたが、ただ「これ、なーんだ」とやるだけでも子供たちは大喜び。知っている形を全て作ってネタ切れになった後も、集まっていたみんなに「どうやるの?教えて」とせがまれて、いつの間にか「子供はもう寝なさい」と声がかかる時間になってしまったほどでした。
子供たちが寝る前の歯磨きに追い立てられると、今度は親戚の大人たちまで、俺にも教えろ私にも教えての大攻勢。いい歳をしたおじさんおばさんたちまでが(失礼^^)、ほらワンコ、こっちはゾウさんだと、とても楽しんでくれました。こんなふうに手影絵は、子供も大人も、みんなの創造力を掻き立ててくれるんですね。
上で紹介したページには動画も付いています。ちょっと見てみましょう。他にもyoutubeなどを探すと、色々な手影絵の動画がたくさん見つかります。この鮮やかさはもはやイリュージョン。マジックのジャンルでイリュージョンと言うと大がかりな仕掛けを駆使したものを言うみたいですが、期待が錯覚を起こさせる「感動錯覚」をうまく用いたこうした演出は、本来の意味でのイリュージョンと言うことができると思います。
こんな鮮やかな影絵が出来たら、一躍子供たちのスターですね。どうですか。やってみたくなってきたでしょう。

こんな本も出ています。著者は最初のURLでご紹介したサイトの影絵ページを監修されている「劇団かかし座」の代表、後藤圭さん。本なら通勤にも持って歩けますから、うまく座席に座れれば、仕事帰りの電車の中などでも密かに練習できるかもしれませんね。
夏の夜は花火なども楽しいですが、影絵はそれとよく似た楽しみを与えてくれます。暗いからこそできる特別な楽しみ。そんなのが共通しているんですね。夏は省電力も兼ねて、テレビも電灯も消して、影絵で楽しんでみませんか。もちろん光源には電気を使いますが、影絵の光源には周囲を無駄に照らしすぎないことが必要ですから、100Vを使うにしても、かなりワット数の小さな電球で事足ります。懐中電灯でもいいですね。反射鏡に白い紙を貼って、光が中心に集束しないようにして照らしてください。
周囲が暗いと、自律神経の制御がだんだん副交感神経に切り替わってきて、子供はおねむになっていきます。そしたらそのまま寝室へ。歯磨きの後で影絵というスケジュールもいいかもしれません。お父さんやお母さんが見せてくれる影絵の思い出は、きっと大人になっても温かな記憶として残っていくことでしょう。
 48pt
48pt
みんなでガヤガヤイエ遊び
僕の家ではwiiのマリオカート等をやって遊んでいます。
操作が良く分からないお母さんや、
バンバン行っている弟など
早さもさまざま、
だけど
差が大きい分会話も多い
どうやってやるの? とか
おいおい、待てよ みたいな
変な声とかも聞こえてくる。
そんないつもとは楽しいことでした。
 48pt
48pt
「風の扉」
小さいころ、暑い夏は、古い戸建の家の窓をすべて開けて暮らしていました。
暑いながらも風を感じながら毎日過ごしていたように思います。
今住んでいるのは集合住宅の3F。
窓を開けても毎日暑いな~と感じて、子供と一緒に「暑い暑い」とエアコンを入れてしまう毎日。
でも先日玄関のドアを少しあけておくと・・・
風がすーっと抜けて行きました。
なんと涼しい!
玄関の「扉」は風の通り道でした。
今までは気付かず閉ざされた「扉」だったのです。
エコが必要とされる今年の夏、風を意識して暮らしていけたらと思っています。
もちろん防犯対策も必要ですが・・・
コメント(0件)